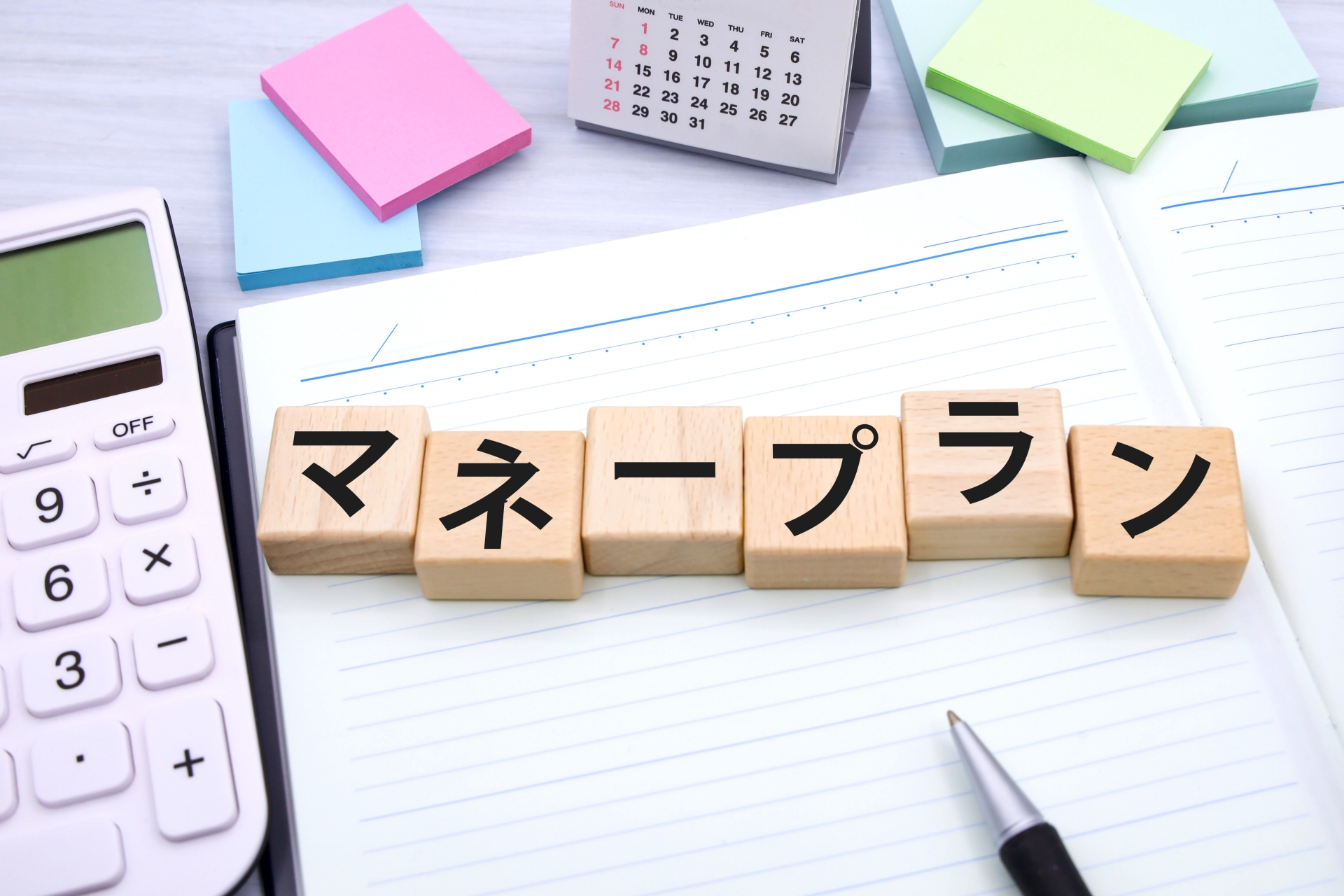はじめに|なぜ今、マネープランの見直しが必要なのか
定年を迎えたあと、多くの人が感じるのが「老後の生活に対する漠然とした不安」です。年金を受け取れるようになっても、「本当にこれだけで暮らしていけるのだろうか?」という疑問は、多くのシニアに共通しています。特に最近では、物価上昇や医療費の負担増など、外的要因による支出の増加が現実の問題となっており、家計の見直しは急務といえるでしょう。
内閣府「高齢者の生活と意識に関する調査(2022年)」によると、「経済的な不安を感じている」と答えた高齢者は約6割を占めており、多くの人が生活費や老後資金について課題を感じています。加えて、65歳以降も働き続けたいという希望を持つ人が増加しているのも、そうした背景があるからです。
しかし、老後のマネープランは「今からでも遅くない」ものです。ポイントを押さえて見直せば、生活の質を落とさずに、安心して暮らすことも十分可能です。本記事では、年金だけに頼らず、健康や社会とのつながりも保ちながら“自分らしい老後”を実現するためのマネープランの考え方と実践方法を紹介します。
1.年金だけでは足りない?老後の収支バランスを見える化しよう
「年金だけでは生活が苦しい」と感じるシニアが年々増えています。実際に、厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、夫婦2人のモデル世帯の年金受給額は月約22万円。一方、総務省の家計調査(高齢夫婦無職世帯)では、月の平均支出は約26万円とされており、月に約4万円の赤字が生じている計算です。
1|まずは「毎月の収支」を書き出してみよう
老後のマネープランを立てるうえで、最初に取り組むべきは「家計の見える化」です。具体的には、以下のような項目ごとに支出を分類し、1カ月あたりの平均を算出してみましょう。
| 支出項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 住居費 | 家賃、住宅ローン、固定資産税など |
| 食費 | 食材費、外食費など |
| 光熱水道費 | 電気・ガス・水道代 |
| 通信費 | スマホ、インターネット、新聞など |
| 保険料 | 医療・介護・生命保険など |
| 医療・介護費 | 通院費、薬代、介護用品など |
| 娯楽・交際費 | 趣味、旅行、友人との食事など |
| その他 | 雑費、交通費、子どもへの援助など |
支出と収入を一覧にすると、「どの項目が多いか」「どこを節約できそうか」が自然と見えてきます。
2|“未来の出費”も想定しておこう
老後は病気や介護のリスクが高まるため、医療・介護費の予備も必要です。例えば、厚生労働省の「人生100年時代における資産形成に関する意識調査」では、70代で医療費が増えると回答した人は全体の約7割。また、介護が始まった場合、自己負担費用として月平均7万8,000円(生命保険文化センター調査)がかかるというデータもあります。
3|可視化することで、冷静な判断ができる
現実を数値で把握すると、不安だけが先行していた気持ちが落ち着くこともあります。「意外とムダな支出が多い」「あと少し収入が増えれば安心できる」といった発見が、次のアクションにつながるのです。
2.安心の老後には“働き方”も重要!収入を増やす選択肢とは
老後の生活費をまかなうためには、「収入の柱」を増やすことも重要なポイントです。年金の不足分を補う手段として最も現実的なのが、「無理のない働き方で収入を得る」こと。現在では、シニアを歓迎する仕事や支援制度も増えており、自分の体力やライフスタイルに合った仕事を選ぶことができます。
1|週2~3日の「短時間勤務」で、生活にハリと収入をプラス
体力や家庭の都合を考えると、週5日のフルタイム勤務は負担が大きいかもしれません。しかし、最近では週2〜3日・1日4時間程度から働ける求人も多く見られます。清掃スタッフ、マンション管理員、調理補助などはその代表例です。
シニア向けの求人を多数掲載する「シルバー人材センター」や「地方自治体の就労支援窓口」では、65歳以上の登録者が活躍しているケースも多く、地域に根ざした働き方が可能です。
2|副業や在宅ワークで「すき間時間」に稼ぐ方法も
外に出るのが難しいという人には、在宅でできる仕事も選択肢に入ります。具体的には、以下のようなものがあります。
・商品モニター、アンケート回答
・データ入力やテープ起こし
・写真、動画編集(スマホでも対応可)
・自分の得意を活かした「スキル販売」(例:note、ココナラ など)
こうした副業は、自分のペースで働けるうえ、体への負担も少ないのが魅力です。
3|「働くこと」がもたらす経済面以外のメリットも
働くことで得られるのは、お金だけではありません。社会とのつながり、日常生活のリズム、役割意識など、心と体の健康に直結する効果もあります。
公益財団法人ニッセイ基礎研究所の調査(2023年)では、「働くことが生きがいにつながっている」と答えた60代・70代のシニアは全体の約65%に上るとの結果もあり、無理のない働き方は、生活の質(QOL)を高める重要な手段といえます。
3.見落としがち?住居・保険・医療費を含めた支出の見直し
マネープランを考えるうえで、収入を増やすことと同じくらい大切なのが「支出を減らす」視点です。特に老後の生活では、一度見直すだけで継続的に節約できる“固定費”が家計を大きく左右します。ここでは、見落としがちな3つのポイントに注目していきましょう。
1|住居費は「今の暮らしに合っているか」を再確認
シニア世代で最も負担が大きくなりがちなのが「住居費」です。家賃が高い物件に住み続けていたり、使っていない部屋が多い広すぎる持ち家に暮らしていたりする場合は、住み替えを検討する価値があります。
たとえば、
・月7万円の家賃 → 月5万円の物件に引っ越せば、年間24万円の節約
・空き部屋が多い → 高齢者向けのコンパクトな賃貸やシェアハウスへの転居で、管理・光熱費も抑えられる
「家賃の低い物件=不便・不安」ではありません。高齢者向けにバリアフリー化された物件や、見守りサービス付きの住宅も増えており、安心・安全に配慮された住まいに移ることで、生活の質が向上するケースも多いです。
2|保険は“入りすぎ”ていないか?見直しで月数千円カットも
現役時代から継続して保険に加入している方は多いですが、老後に入っておくべき保険と、そうでないものを見直す必要があります。
たとえば、
・医療保険やがん保険 → 高額療養費制度や自治体の助成で十分カバーできる場合あり
・生命保険 → 子育てが終了していれば大きな保障は不要なことも
保険の内容が現状と合っていなければ、「解約」や「減額」も視野に入れて再検討しましょう。月に3,000~5,000円の節約になることも珍しくありません。
3|医療費は制度の活用と“予防”でコントロール
年を重ねるにつれ、医療費の負担は増えていきます。ただし、高齢者にはさまざまな支援制度があります。
・後期高齢者医療制度(75歳以上対象)
・高額療養費制度(月額の自己負担限度額が定められている)
・自治体の医療費助成制度
加えて、健康診断の受診・日々の運動・食事管理などの「予防」も、将来的な医療費の抑制につながります。健康維持は節約にも直結する、大きな投資といえるでしょう。
4.頼れる制度・サービスを活用しよう!支援制度と相談窓口まとめ
老後のマネープランは、自分一人で抱え込む必要はありません。国や自治体には、高齢者を支援する制度や無料の相談窓口が多く用意されており、それらをうまく活用することで、経済的な不安を和らげることが可能です。
ここでは、特に知っておきたい支援制度や相談先をまとめて紹介します。
1|高齢者向けの公的支援制度
| 制度名 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 月ごとの医療費に上限が設定され、超過分が払い戻される制度 | 全国健康保険協会、市区町村 |
| 老齢加算(生活保護) | 生活保護を受ける高齢者に対しての加算支給 | 福祉事務所 |
| 介護保険サービス | 要介護認定を受けた人が介護サービスを1~3割の自己負担で利用可能 | 市区町村の介護保険課 |
| 障害者控除 | 要介護者が対象となる場合、所得税や住民税が軽減される | 税務署または市区町村 |
2|無料相談できる窓口やサービス
「どこに相談していいかわからない」という場合は、以下のような高齢者向けの総合相談窓口を利用するのが安心です。
・地域包括支援センター
→ 介護・健康・暮らし・お金に関することをワンストップで相談できる。各市区町村が設置。
・社会福祉協議会
→ 緊急小口資金の貸し付けや、福祉サービスの紹介などを実施。住民の生活支援に特化。
・年金事務所
→ 年金の受給額・手続き・繰下げ受給の相談が可能。全国に設置。
・消費生活センター
→ 高齢者を狙った詐欺や契約トラブルの相談対応。シニア世代のトラブルが増えている今、重要な相談先。
3|制度を知ることで「選択肢」が増える
これらの制度やサービスを活用することで、日々の不安や将来への備えに具体的な解決策が見えてきます。「申請が面倒そう…」と思われがちですが、多くの自治体では窓口で丁寧に教えてくれる体制が整っています。知らないままで損をしないように、まずは一度問い合わせてみることが大切です。
5.無理なく実践!今日から始めるマネープランの5ステップ
老後の不安を減らすためのマネープランは、「特別なお金の知識が必要」と思われがちですが、実はちょっとした行動の積み重ねが大きな安心につながるものです。ここでは、無理なく始められる実践的な5つのステップをご紹介します。
ステップ1:1カ月の家計簿をつけてみる
まずは、自分が毎月どれだけ使っているかを把握しましょう。紙の家計簿でも、スマホアプリ(「マネーフォワード ME」「Zaim」など)でもOKです。
・支出の中身(固定費と変動費)
・不要な支出
・思っていたよりかかっている項目
これらを“見える化”することが、マネープランの第一歩です。
ステップ2:支出を「固定費」から見直す
食費や日用品よりも、まずは固定費の削減が効果的。たとえば…
・スマホの料金プランを見直す
・サブスクを解約する
・高額な保険を減額、解約する
これだけでも、月5,000〜1万円の節約につながるケースもあります。
ステップ3:収入の“もう一つの柱”をつくる
前章で紹介したように、週に数日の仕事や在宅ワークは、年金以外の安定収入になります。
・体力に合った仕事(マンション管理・清掃・配膳補助など)
・好きを活かせる副業(動画編集・写真加工・スキル販売)
健康維持や社会とのつながりにもなり、生活にハリが出ます。
ステップ4:相談機関を利用して情報収集
「知らなかった」で損をしないために、制度や支援サービスは積極的に活用を。
・地域包括支援センターで、生活全体の相談
・年金事務所で、年金の受け取り方を再確認
・社会福祉協議会で、生活費の一時貸付制度などもチェック
プロのアドバイスをもらうことで、より安心して行動できます。
ステップ5:3カ月ごとに“見直し”を習慣化
一度立てたマネープランも、定期的に振り返ることが大切です。
・実際に節約できたか
・支出の変化(物価上昇など)に対応できているか
・体調の変化によって働き方を変える必要があるか
3カ月に1度のペースで見直せば、ムリなく軌道修正できます。
少額からでも「NISA」で老後資金を育てる
節約や就労と並行して、少しずつでも資産を育てる工夫を取り入れてみましょう。特に2024年から制度が大きく変わった新NISA(少額投資非課税制度)は、シニア世代にも注目されています。
・年間360万円まで非課税で投資可能(つみたて投資枠+成長投資枠の併用可)
・株式や投資信託の利益が非課税
・自分のペースで少額から始められる(例:毎月1,000円~)
例えば、月1万円をNISA口座で積立て、年5%で複利運用した場合、10年間で約155万円になります(元本120万円+利益)。※あくまでシミュレーションです。
「投資は難しそう」と感じる方は、銀行や証券会社、金融庁の公式サイトなどで情報収集をし、無理のない範囲で、勉強しながら始めてみるのがよいでしょう。
まとめ|これからの人生を安心して生きるために
老後の暮らしにおけるマネープランは、「特別な知識がある人」だけのものではありません。年金収入の範囲内でどう暮らすか、収支のバランスをどう整えるかを自分なりに考え、できることから少しずつ行動に移すことが、将来への不安を和らげる一番の近道です。
本記事で紹介した内容は、どれも今日から取り組めるものばかりです。
・家計を「見える化」して無駄を把握する
・健康や生活スタイルに合った仕事で収入を補う
・固定費や保険を見直して支出を減らす
・制度や相談窓口を活用して知識と選択肢を増やす
そして何より大切なのは、「一人で抱え込まないこと」です。年齢や収入にかかわらず、行動した人から安心と充実を手に入れられる。それが、人生100年時代を前向きに生き抜くためのヒントになります。
焦らず、でも確実に。あなた自身のペースで、“自分らしい安心のマネープラン”を育てていきましょう。
安心の収入源を見つけたい方へ。シニア歓迎の求人が豊富なサイト「キャリア65」で、あなたに合った仕事を探してみませんか?