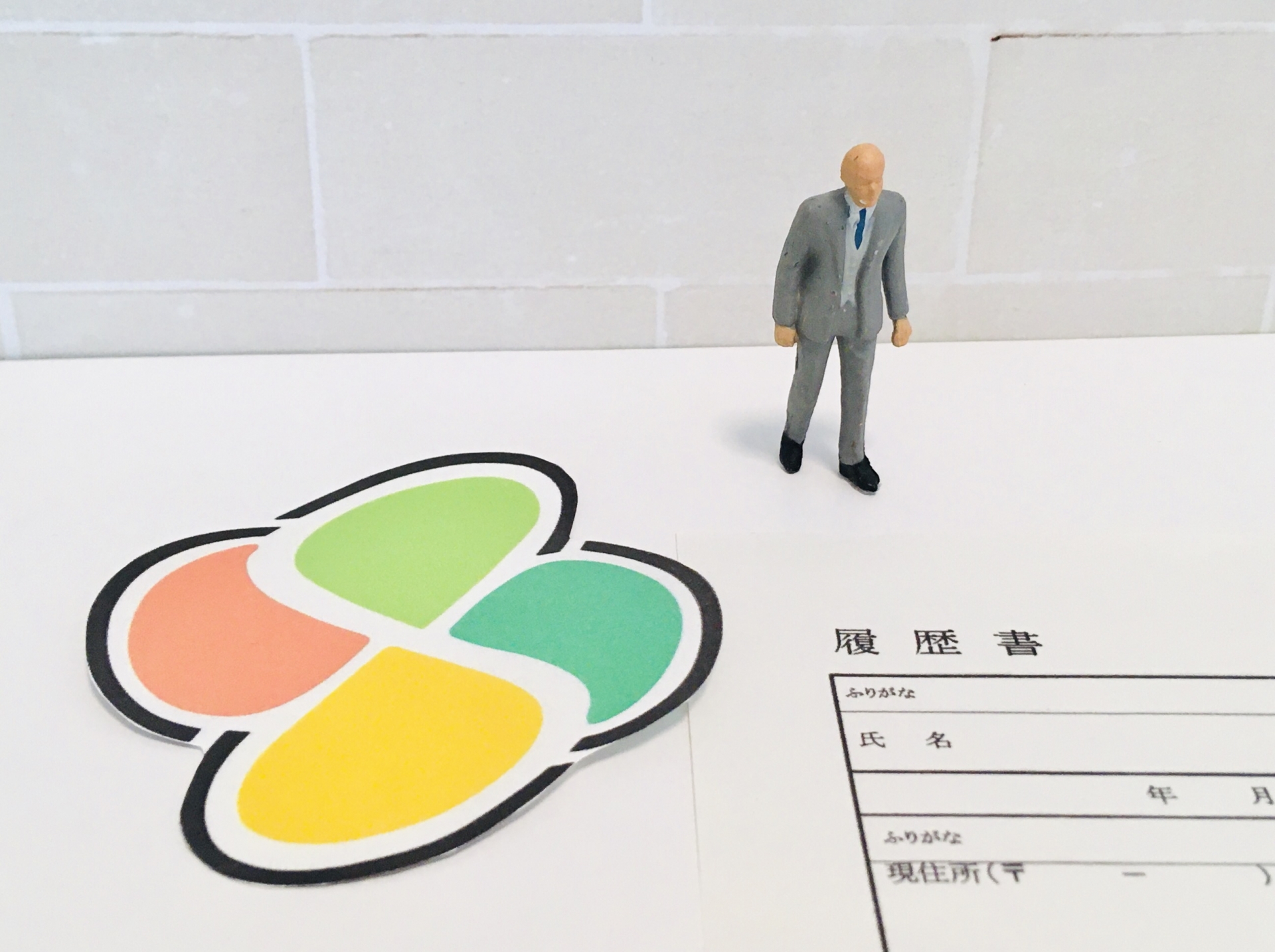1. はじめに|なぜ今「シルバー人材センターの活用」が注目されるのか
少子高齢化と労働人口の減少が進む中、企業が安定した人材確保を行うことは年々難しくなっています。特に中小企業や地方の事業所では、「定年退職後の人材流出」によるノウハウの断絶が深刻な課題となっています。こうした状況の中で、再び注目を集めているのが「シルバー人材センターの活用」です。
シルバー人材センターは、各自治体や公益法人が運営する高齢者の就業支援機関で、60歳以上のシニアが登録し、企業や家庭などの依頼に応じて請負・委任契約で仕事を行います。公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会の「事業概要(2024年)」によると、全国のセンター登録者は約75万人。年々増加傾向にあり、就業意欲の高いシニア人材の受け皿として重要な役割を担っています。
この仕組みを活用することで、企業側は採用コストを抑えながら即戦力を確保できるほか、短期間・スポット的な業務依頼にも柔軟に対応できます。さらに、労働契約ではなく請負・委任契約を結ぶ形のため、社会保険や雇用保険の手続きも不要で、法的リスクを最小限に抑えることが可能です。
一方、働くシニアにとっても、地域での経験やスキルを活かしながら「無理なく」「やりがいを持って」働ける環境が整っています。週数日・数時間の勤務など、自身の体力や生活ペースに合わせて働ける点も大きな魅力です。
こうした双方のメリットが重なり、いまやシルバー人材センターは「人手不足対策」「多様な働き方推進」「地域共生社会の実現」を支える仕組みとして、行政・企業の両面から注目を集めています。
2. シルバー人材センターの仕組みと特徴|請負・委任契約の違いを理解しよう
シルバー人材センターの最大の特徴は、「雇用契約」ではなく「請負」または「委任契約」で成り立っている点です。これは一般的なパート・アルバイト雇用とは異なる仕組みであり、企業側のリスク軽減や手続き簡略化につながっています。
■ 請負・委任契約とは?
・請負契約:作業の「結果」に対して報酬を支払う契約形態。たとえば「この部品を100個組み立てて納品する」といった成果物に対する契約です。
・委任契約:作業の「遂行」に対して報酬を支払う契約形態。たとえば「施設の受付業務を週3回担当する」など、作業の結果よりも過程に重きを置く業務が該当します。
どちらの場合も、企業とセンターの間で直接雇用関係は発生しません。 したがって、企業側は社会保険や労働保険の加入義務を負わず、就業管理の責任もセンターが担います。
契約・報酬の流れ
業務依頼を受けたセンターは、登録しているシニア会員の中から適任者を選定します。仕事が完了すると、センターが企業に報酬を請求し、そこから手数料を差し引いた金額を会員に支払う仕組みです。センターが仲介者として間に入ることで、トラブル防止や品質管理もスムーズに行われます。
法的な位置づけ
シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)第40条」に基づき設立されており、全国に約1,200カ所(加盟センター1,217カ所/令和5年度)存在します。
行政の支援を受けた公益性の高い仕組みのため、安心して活用できる点も企業にとっての利点です。
他の人材活用制度との違い
派遣や業務委託と比べると、シルバー人材センターは営利目的ではなく地域貢献・社会参加を目的とした公的制度という点が大きな違いです。そのため、料金は比較的低く、短期的な仕事でも対応が可能です。
一方で、常勤や専門性の高い業務には向かないケースもあるため、業務内容の見極めがポイントになります。
3. 企業側のメリット|採用コスト削減・労務リスクの回避・地域貢献
シルバー人材センターの活用は、単なる「人手不足対策」にとどまりません。企業にとっては、コスト削減・リスク軽減・社会的評価の向上という3つの側面で大きなメリットをもたらします。
採用・人件費コストを大幅に削減できる
シルバー人材センターを通じた依頼では、求人広告費や面接対応、人事労務管理といった採用に伴うコストをほぼゼロに近づけることができます。
マイナビバイト「採用費用に関する調査(2023年)」によると、1人のアルバイト採用にかかる平均コストは約10万円前後とされています。
一方、シルバー人材センター経由での依頼は、1回あたり報酬額の10〜15%程度の手数料のみ。求人広告費や面接対応の手間も不要で、必要なときに必要な人材を確保できるのが大きな強みです。
労務リスクを最小限に抑えられる
センターの契約形態は「請負」または「委任」であるため、企業は雇用主としての責任を負いません。社会保険・雇用保険の手続きや有給休暇付与などの義務も発生しないため、労務リスクの軽減が可能です。
また、労働災害が発生した場合でも、センターが独自に加入する「シルバー保険」により補償が行われます。こうした制度設計により、企業は安心して業務を委託できるのです。
経験豊富な人材を即戦力として活用できる
シルバー人材センターの登録者は、定年後も働く意欲の高い60歳以上の方々。多くが、製造、事務、営業、管理職などで長年の実務経験を積んだ人材です。
そのため、新人教育の手間がかからず、現場にすぐ溶け込める人材が多いのが特徴です。特に、「安全意識が高く、責任感が強い」という声は多く、短期・定期業務でも高い信頼を得ています。
地域社会との関係強化・企業イメージ向上
シルバー人材センターを通じた人材活用は、地域の高齢者雇用を支援する社会的意義もあります。
企業が地域に貢献する姿勢を示すことで、自治体との連携が深まり、「地域密着型企業」「社会的責任を果たす企業」としての評価も向上します。CSRやESGの観点からもプラスの影響が期待できます。
4. 活用できる業務例|製造・清掃・軽作業・庶務などの具体事例
シルバー人材センターでは、全国共通で多岐にわたる業務を取り扱っています。依頼できる範囲は「危険・有害・責任の重い業務」を除いた補助的・周辺的な作業が中心ですが、その分、幅広い業種・職種で活用されています。ここでは代表的な業務例を紹介します。
製造・物流分野:熟練作業や軽作業のサポートに最適
製造工場では、組立・検品・梱包といった単純作業の工程分担に活用されるケースが多く見られます。熟練のシニア人材は手先が器用でミスが少なく、品質管理の安定化に寄与します。
また、物流倉庫では仕分けや在庫整理、配送補助などの業務でも活躍。繁忙期の短期人材確保にも柔軟に対応できる点が企業に評価されています。
ビルメンテナンス・清掃業務:責任感の高さが強み
オフィスビルや商業施設、公共施設などの清掃・設備点検なども、シルバー人材センターが得意とする分野です。登録者の多くは几帳面でコツコツ型の性格の方が多く、細やかな配慮が求められる清掃現場では非常に重宝されます。
さらに、朝夕の短時間シフトや週数日勤務といった柔軟な働き方が可能なため、企業側もコストと稼働時間を最適化できます。
事務・庶務・受付などのオフィス業務
一般企業や行政機関では、書類整理、データ入力、電話応対などの庶務・事務補助業務にも多くのシニア人材が従事しています。特に定年後も事務職経験がある方は、ビジネスマナーや電話応対スキルが高く、即戦力として現場の安定化に貢献しています。
また、来客対応や受付業務では、穏やかで丁寧な対応が顧客満足度の向上につながるケースも少なくありません。
公共・地域サービス:社会的意義の高い分野
公園や学校の清掃、通学路の見守り、自治体主催イベントの運営補助など、地域社会を支える業務も多数存在します。これらの仕事は、地域住民との交流や世代間のつながりを生む役割を果たし、企業としても地域貢献活動の一環として位置づけられる点が特徴です。
活用の幅を広げるコツ
業務を依頼する際は、「誰にでもできる仕事」ではなく、“熟練者だから任せたい仕事”を意識することが重要です。たとえば、工具の扱いに慣れた元職人に修繕業務を任せる、元事務職に資料作成を任せるなど、経験を活かす配置を行うことで、作業品質と満足度の両方が高まります。
5. 活用までの流れ|問い合わせから契約までのステップと期間の目安
シルバー人材センターを初めて利用する企業でも、手続きは非常にシンプルです。契約から業務開始までは、一般的に1〜2週間程度で完了します。ここでは、実際の流れをステップごとに見ていきましょう。
STEP1:センターへの相談・依頼内容の確認
まずは、事業所所在地を管轄する地域のシルバー人材センターへ問い合わせます。
全国に約1,200カ所のセンターがあり、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会の公式サイト(https://www.zsjc.or.jp/)から検索可能です。
依頼時には以下の内容を明確に伝えるとスムーズです。
・どんな業務を依頼したいか(作業内容/頻度/期間)
・どのくらいの人数が必要か
・実施場所/時間帯
・希望するスキルや経験
担当者が内容をヒアリングし、センター内で実施可能かどうかを確認します。
STEP2:センターによる人選・見積もり提示
センターでは、登録会員の中から依頼内容に最適な人材を選定します。経験・技能・希望勤務時間などをもとに候補者をマッチングし、概算の費用見積もりを提示します。
報酬は業務内容や地域ごとに異なりますが、全国シルバー人材センター事業協会の統計(令和5年度)によると、1日あたりの平均報酬は約3,600円。
多くの業務が1日3〜4時間程度のため、時給換算では概ね900〜1,200円前後が一般的な水準といえます。
STEP3:契約の締結(請負または委任契約)
企業とセンターの間で、請負または委任契約を締結します。
この契約では、「労働時間」や「雇用条件」を明記する必要はなく、業務内容・期間・報酬・支払方法を定めるのが一般的です。契約書はセンターが作成するため、企業側の手間はほとんどありません。
STEP4:業務開始・進捗フォロー
契約後、センターが選任した会員が現場で業務を開始します。作業の品質や進捗については、センター職員が定期的にフォローし、企業側の負担を軽減します。
業務終了後には、センターが企業に対して請求書を発行し、企業はセンターに支払います。センターはその中から手数料を控除し、会員に報酬を支払う仕組みです。
期間の目安
・初回相談〜契約締結:約3〜7日
・契約締結〜業務開始:1週間前後
依頼内容や規模によっては、即日対応可能なセンターもあります。短期・スポットの仕事であっても、柔軟に対応できるのが大きな強みです。
6. 活用時の注意点|労働契約との違い・安全管理・トラブル防止のポイント
シルバー人材センターの活用は多くのメリットがありますが、通常の雇用契約とは異なる制度であるため、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。ここを押さえておくことで、トラブルを防ぎ、より円滑に制度を活用できます。
労働契約ではないことを理解する
まず最も重要なのは、センター会員と企業との間に「雇用関係が発生しない」という点です。
そのため、企業側は労働基準法や労働契約法の適用対象外となります。つまり、
・労働時間の管理
・時間外手当/休暇の付与
・社会保険/雇用保険の加入
などの義務は発生しません。
ただし、「指揮命令」を直接行ってしまうと、雇用関係とみなされるリスクがあるため注意が必要です。現場での指示はセンター職員を通じて行い、契約上の役割分担を明確にしておくことが重要です。
安全管理体制を整える
シニア人材の就業では、転倒・熱中症などの軽微な労災リスクが想定されます。
センターは「シルバー保険」に加入しており、万が一の事故にも備えていますが、企業としても次のような配慮が求められます。
・現場の危険箇所を事前に確認/共有する
・重作業/高所作業を依頼しない
・休憩/水分補給を促す
・安全教育をセンター職員と連携して行う
こうした基本的な配慮が、双方の信頼関係を築くうえで欠かせません。
トラブルを未然に防ぐ契約設計
シルバー人材センターは公益法人であり、トラブル対応のルールも整備されていますが、依頼時には以下の3点を明記しておくと安心です。
1.作業範囲と責任範囲(「どこまでやるか」を明確に)
2.報酬の算定基準(作業量・時間・成果物の定義)
3.作業時間帯・立入範囲(安全性・効率性の観点から)
これらを事前に共有することで、誤解や作業漏れを防ぎ、長期的な信頼関係を築くことができます。
禁止されている業務もある
高齢者の安全を守るため、センターでは以下のような危険・責任の重い業務は原則として受託できません。
・建設現場での高所作業や重量物運搬
・医療/介護現場での身体介助
・送迎中の運転など、第三者に損害を与える可能性のある業務
これらは労働災害リスクが高いため、センターでは代替作業(清掃・備品補助など)で対応するケースが一般的です。
信頼関係と明確なルールが成功のカギ
シルバー人材センターの活用は、「任せっぱなし」ではなく、センターとのパートナーシップ型の関係構築がポイントです。
制度の仕組みを正しく理解し、双方に無理のない範囲で役割を分担することで、企業とシニアの双方にとって満足度の高い結果が得られます。
7. まとめ|シルバー人材センター活用で広がる“多様な働き方”の未来
シルバー人材センターの活用は、単なる人材確保の手段にとどまらず、企業と地域社会が共に成長していく新しい雇用モデルとして注目を集めています。
少子高齢化の進行により、若年層だけで企業を支えることは難しくなっています。その中で、シニアの経験・知恵・人間力を活かすことは、組織の持続可能性を高める重要な経営戦略の一つです。
企業側にとっては、採用コストの削減や労務リスクの回避だけでなく、地域から信頼される企業ブランドの形成にもつながります。一方、働くシニアにとっては、「まだ社会の役に立てる」「自分のペースで働ける」という生きがいが得られます。まさに、双方にとって“Win-Win”の関係です。
また、近年では企業がセンターを通じてOJT指導や新人教育の補助業務を依頼するケースも増えており、「人材育成×地域活性」の観点からも価値が拡大しています。短期・軽作業に限らず、「人を育てる力」を持つシニアの力を活かす活用法も、これからのトレンドと言えるでしょう。
国も「生涯現役社会」を掲げ、高齢者の就業促進に向けた支援制度を強化しています。こうした流れの中で、シルバー人材センターはますます重要な役割を担っていくはずです。
企業としては、一度試験的に依頼してみることで、その実用性と安心感を実感できるでしょう。
シニア人材の活用をもっと手軽に。採用コスト0円で始められるシニア向け求人サイト「キャリア65」で、経験豊富なシニア人材との出会いを実現しませんか?