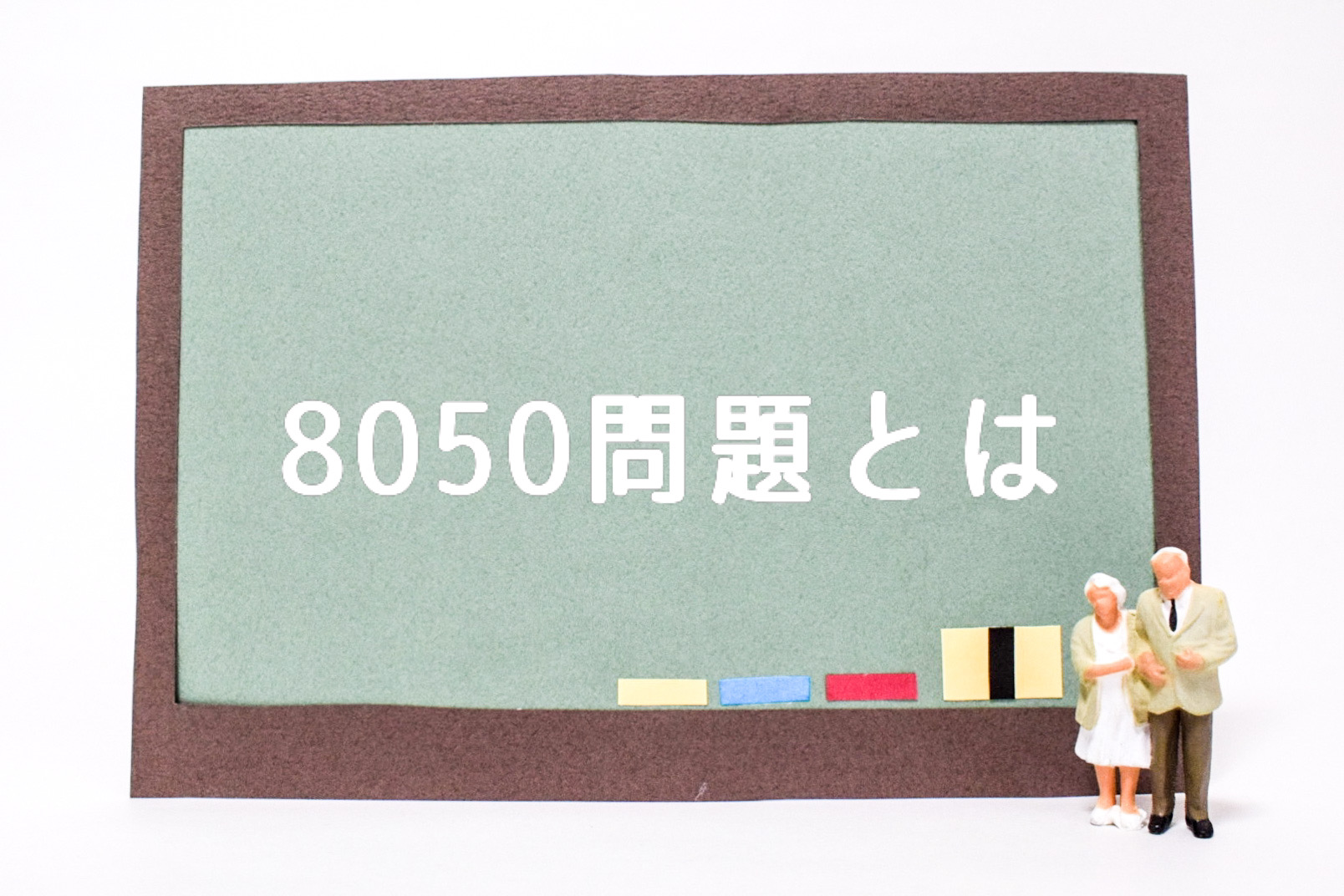1.そもそも「8050問題」とは?背景と現状をおさらい
高齢の親と中年の子の共倒れ
「8050問題」とは、80代の親が、50代の子どもと同居しながら、双方が社会的に孤立し、経済的・精神的に困窮する状況を指します。背景には、長期にわたるひきこもりや就労困難など、子どもの自立が叶わないまま高齢化が進んでしまったという現実があります。
たとえば、親が年金で生活を支えているものの、その年金も十分とはいえず、医療費や介護費用が増えていく一方で、子どもは働く意欲があってもブランクの長さや年齢を理由に再就職が難しい――。このような「共倒れ状態」が日本全国で深刻化しています。
2023年時点で、40歳以上のひきこもり人口は約74万人にのぼり(内閣府調査)、高齢化した親との生活に苦しむ声も多く寄せられています。
「引きこもり」支援が追いつかない理由
支援の手が届かない背景には、家庭の問題が表面化しにくい点があります。ひきこもっている子どもが社会との接点を完全に絶たれていると、行政や支援団体が存在すら把握できず、支援が始まるまでに長い時間を要します。
さらに、親自身も「世間体」や「恥ずかしさ」から、外部に相談しないケースが多いのも実情です。結果として、問題は潜在化し、ある日突然「孤独死」「介護放棄」などの悲劇を引き起こすこともあります。
2.「9060問題」とは?進行する高齢化がもたらす次の課題
親が90代、子どもが60代の新たな共依存
「8050問題」よりさらに深刻な段階として、近年注目されているのが「9060問題」です。これは90代の親と60代の子どもが共に高齢となり、どちらも支援を必要とする状況のことを指します。
この問題の特徴は、子ども自身もすでに高齢者となっており、体力や健康に不安を抱えながら介護を担っている点にあります。親は要介護状態、子どもも定年退職後で収入源が年金のみというケースが多く、経済的にも精神的にも限界を迎える家庭が少なくありません。
また、60代の子どもは「自分が年老いた親の介護をしている」立場である一方、自分自身の健康や老後の不安も重なり、心身ともに疲弊しやすくなっています。
「老老介護」から「超・老老介護」へ
以前から問題視されていた「老老介護」は、65歳以上の高齢者同士による介護を意味していました。ところが、「9060問題」の深刻化により、今や“90代の親が60代の子に介護される”という「超・老老介護」状態に突入しています。
このような家庭では、介護者自身が腰痛や糖尿病、認知症などを抱えていることも珍しくなく、介護中の転倒や事故、介護疲れによる共倒れが現実となっているのです。
厚生労働省の「国民生活基礎調査(2022年)」によると、在宅で要介護者を世話している人の約3割が60代以上であり、今後さらにその割合が増えることが予測されています。
社会全体が高齢化する中で、「支える人も支えられる人も高齢者」という構図は、今後ますます日本の社会課題として大きな影響を与えるでしょう。
3.なぜ「8050問題」は「9060問題」へ移行したのか
長寿社会の“副作用”としての介護リスク
「8050問題」が「9060問題」へと進行した背景には、日本社会の急速な高齢化があります。平均寿命は年々延び、2023年時点では男性81.05歳・女性87.09歳(厚生労働省「簡易生命表」)と、世界でもトップクラスの長寿国家となっています。
一方で、健康寿命とのギャップ、つまり「日常生活に制限が出てくる年齢」はそれよりも短く、介護が必要になる期間が延びています。その結果、80代で介護を受ける側だった人が90代まで生きるようになり、子どももまた高齢に達した状態で支える「9060問題」が現実となったのです。
もともと家庭内で親子の共依存が続いていた場合、年月を経て共に高齢者となっても、その関係性が断ち切れず、問題がさらに深刻化してしまうケースが多く見られます。
年金・収入の限界と生活困窮の連鎖
もう一つの重要な要因は、経済的な問題です。60代の子どもが年金を受け取る年齢になっても、その金額は親世代より少ないケースが多く、二人分の生活費をまかなうのが難しい現実があります。
とくに無職や非正規雇用のまま高齢期に突入した人々にとっては、収入の柱が極端に弱く、親の年金に頼る「逆依存」の状態に陥ることも少なくありません。親の死亡や介護費用の増大によって、一気に生活が破綻してしまう危険性すらあるのです。
このような背景が、8050問題を静かに、そして確実に9060問題へと変化させています。誰もが歳をとる時代。親も子も「支援される側」になり得るという現実に、私たちは目を向ける必要があります。
4.この問題は他人事ではない!70代でも今からできる“備え”とは
自分の足で動けるうちに「仕事」や「役割」を持つ
「9060問題」は、遠い誰かの話ではありません。60代、70代の今、自分がまだ元気に動けるからこそ、“支える側”としてだけでなく、いずれ“支えられる側”になることも視野に入れた備えが必要です。そのために重要なのが、「社会との接点を持ち続けること」です。
たとえば、定年後にシニア向けの仕事に就くことで、以下のようなメリットがあります。
・収入面での安心(年金に加える形で家計を支える)
・身体を動かす習慣(健康維持)
・人との関わりによる心の安定(孤独感の予防)
実際に厚生労働省の「高年齢者の雇用状況等調査(令和4年)」によると、70歳以上でも就業している人の割合は約27%にのぼり、多くの人が「働くこと=生きがい」と感じていることがわかります。
仕事といっても、重労働をする必要はありません。施設管理、警備、配達補助、図書館の案内など、体力に合った仕事で「役割」を持つことが、将来の孤立や困窮のリスクを減らすことにつながります。
社会とのつながりが、心身の健康を支える
「8050問題」や「9060問題」の本質は、「孤立」と「支援不足」にあります。ですから、自分自身が孤立しないことが、将来に向けた最大の“予防”になります。
たとえば、
・地域の活動に参加する
・趣味のサークルやボランティアに関わる
・地域包括支援センターと日頃からつながりを持つ
といった行動は、自分の「見守りネットワーク」を自然と広げることになります。
また、自分が積極的に地域に関わることで、周囲の同世代や次世代と交流が生まれ、「経験を活かす場」にもなります。それが自信となり、心の安定にもつながります。
60代、70代はまだまだ「備えられる世代」。今の一歩が、将来の自分と家族を守る力になります。
5.支える側・支えられる側、どちらにも役立つ相談先・制度一覧
「8050問題」「9060問題」といった複雑な家庭の課題に直面したとき、一人で抱え込まず、専門機関に相談することが非常に重要です。ここでは、高齢者本人やその家族、支援者にとって頼れる主な相談窓口や制度をご紹介します。
地域包括支援センター
各自治体が設置している「地域包括支援センター」は、高齢者に関する困りごとを総合的に受け止めてくれる相談窓口です。介護サービスの利用や福祉制度の紹介はもちろん、日常生活のちょっとした不安にも耳を傾けてくれます。
相談は無料で、対象者本人だけでなく家族からの問い合わせにも対応しています。「この状況、誰に相談したらいいのかわからない」というときは、まずここへ連絡してみることをおすすめします。
引きこもり地域支援センター・家族会
「8050問題」「9060問題」の根底には、長年の引きこもりや社会的孤立があります。そのような問題に対応するのが「ひきこもり地域支援センター」や「家族会」です。
引きこもり本人へのアプローチ方法、親の高齢化への不安、きょうだい間の負担など、センシティブな悩みに対して、支援のプロが継続的に寄り添ってくれます。家族会では、同じ立場の人たちと出会い、孤立感を和らげることもできます。
高齢者就労支援サービス
自立の第一歩として「働くこと」を選ぶ高齢者に対しては、各種の就労支援制度が用意されています。たとえば以下のようなサービスがあります。
・シルバー人材センター:60歳以上の方が軽作業や短期業務に従事できる仕組み。
・ハローワークの高齢者窓口:年齢に応じた仕事紹介や職業訓練制度の案内。
・民間のシニア向け求人サイト:シニア歓迎の企業とマッチング可能。
特に年金だけでは生活が不安な人にとって、こうした就労支援は“生活の糸口”となり得ます。自身の経験やスキルを活かしながら、再び社会とつながることができるのです。
6.まとめ|「8050問題」「9060問題」に向き合うために今できること
高齢化社会は“全員参加”の課題
「8050問題」や「9060問題」は、特定の家庭だけの問題ではありません。いまや日本のどの地域でも起こり得る“社会全体の課題”です。
90代の親と60代の子という関係性は、今後さらに拡大していくことが予測されており、私たち一人ひとりが「無関係ではいられない」時代がすでに始まっています。
こうした課題に対処するには、行政や専門機関だけでなく、地域・家族・本人それぞれの行動が欠かせません。なかでも重要なのは、「誰かが困っている」と気づいたときに、声をかける・つなぐ・相談するという“ゆるやかな見守り”の文化を広げることです。
小さな一歩が、社会的孤立の連鎖を防ぐ
60代、70代の今だからこそ、自分自身ができる備えがあります。たとえば――
・健康なうちに仕事やボランティアで社会とつながっておく
・もしもの時に相談できる窓口を知っておく
・同世代や若い人との交流を持ち続ける
・子ども世代との会話を重ね、無理なく支え合える関係を築く
こうした“小さなアクション”の積み重ねが、将来的な孤立や共倒れを防ぐ大きな防波堤になります。
「8050問題」や「9060問題」は決して遠い未来のことではありません。今の自分の行動が、明日の安心をつくります。
そして、あなた自身が動くことで、周囲の人にも良い影響が波及する――そんな“支え合える社会”を目指して、できることから始めてみませんか。
未経験から始められる仕事が満載!社会とつながる一歩として、シニア歓迎の求人をシニア向け求人サイト「キャリア65」で今すぐチェックしてみませんか?