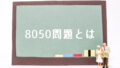1.なぜ「物忘れ」が気になるのか?高齢者に多い不安とは
加齢による記憶力の変化はどこまでが正常?
年齢を重ねるにつれ、「人の名前が出てこない」「何を取りに来たのか忘れた」といった物忘れが増えるのは、多くの人が経験する自然な変化です。これは加齢による脳の情報処理スピードの低下や注意力の低下が原因であり、いわゆる「加齢による健忘」と呼ばれる正常な現象です。
この段階では、何かを思い出せないことがあっても、時間が経てば思い出せる、ヒントがあれば気づける、といった特徴があります。また、日常生活に支障をきたすほどではなく、家計の管理や会話なども問題なく行えるのが一般的です。
「もしかして認知症かも…」と思うタイミングとは
一方で、次のような状態が見られた場合は注意が必要です。
・数分前の出来事を完全に忘れてしまう
・話のつじつまが合わなくなってきた
・同じ話を何度も繰り返す
・日時や場所の感覚があいまいになる
・家族や友人との関係がうまくいかなくなってきた
これらの兆候が現れると、加齢によるものではなく、認知症の初期症状である可能性も考えられます。特に「最近、同じことを何度も聞かれる」「何か変だと家族から言われた」というような外部からの指摘があった場合は、早期にチェックを行うことが大切です。
「自分は大丈夫」と思っていても、知らないうちに変化が起きていることもあります。認知症は早期発見・早期対応が非常に重要であり、その第一歩が自己診断テストです。
2.認知症自己診断テストとは?どんなことがわかるのか
医療機関が使う簡易検査の内容とは
認知症の診断には、医師による問診やMRIなどの画像検査が必要ですが、その前段階として、簡易的な認知機能検査が広く活用されています。代表的なものに「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や「MMSE(Mini-Mental State Examination)」があります。
例えば「HDS-R」は以下のような質問で構成されており、総得点は30点満点です。
・今日の日付や曜日は?
・今いる場所はどこですか?
・簡単な単語を覚えて、あとで思い出せるか?
・数字を逆から言えるか?
・身近な物の名前を答えられるか?
こうした質問を通じて、記憶力・注意力・言語理解力など、認知機能の基本的な能力を測定します。点数が一定の基準を下回ると、認知症の疑いがあるとして、さらに精密な検査を勧められます。
なお、厚生労働省の資料によると、認知症の疑いがある高齢者のうち、約6割はまだ診断や支援を受けていないとされています(出典:厚労省「認知症施策推進大綱」令和元年)。
自宅でできる無料チェックリストの紹介
最近では、インターネット上でできる認知症自己診断テスト(セルフチェックも充実しています。医療機関や地方自治体、認知症支援団体などが提供しており、スマートフォンやパソコンがあれば誰でも簡単に試せます。
例として、以下のような質問が出されます。
・財布や鍵など、よく置き忘れることがある
・同じ話を何度もすることがある
・以前より怒りっぽくなった気がする
・趣味や外出への関心が薄れてきた
これらの質問に「はい」「いいえ」で答えるだけで、自分の状態を簡易的にチェックすることができます。
注意点として、これらのチェックリストはあくまで「気づき」のためのものであり、診断結果ではないことを理解しておきましょう。ただし、スコアの傾向から「専門医への相談が必要かどうか」の目安にはなります。
3.実際にやってみよう!簡単セルフチェックテスト【実例つき】
代表的な認知機能チェックの設問例
ここでは、自宅で試せる認知症自己診断テストの一例を紹介します。あくまで簡易的なセルフチェックですが、日々の状態を把握するヒントになります。
以下は、公益社団法人 認知症の人と家族の会 や一部の自治体が推奨する簡単なチェック項目例です(出典:厚生労働省「認知症ケアパス」より一部改変)。
■ 認知症セルフチェック10問
各項目に「はい」または「いいえ」で答えてみましょう。
1.物の名前がすぐに出てこないことがある
2.財布や鍵など、いつも使う物をよく置き忘れる
3.今日の日付や曜日がわからなくなることがある
4.昔の話はよく覚えているが、最近の出来事を思い出せない
5.同じ話を何度も繰り返してしまう
6.約束の時間や場所を間違えることが増えてきた
7.身だしなみを整えることに無関心になってきた
8.人との交流を避けるようになった
9.簡単な計算で間違えることが多くなった
10.自分では「少しおかしいな」と感じている
「はい」が4つ以上あった場合、加齢による物忘れ以上の可能性があり、医療機関での相談を検討してみましょう。
テスト結果から読み取れることと注意点
このようなセルフチェックは、あくまで初期の「気づき」を得るためのツールです。診断や治療方針を決めるものではありませんが、自分の変化に目を向ける大切なきっかけになります。
また、テストの結果よりも「家族や周囲の反応」も重要なサインです。本人が気づかなくても、日常の様子に違和感を感じている場合は、それを素直に受け入れて、次のステップに進むことが予防や早期対応につながります。
一方で、「テストで不安な結果が出た=認知症が確定」ということではありません。うつ病やストレス、睡眠不足などによっても一時的な記憶障害は起きるため、必要に応じて専門機関に相談しましょう。
4.認知症の不安を減らすためにできること
予防に役立つ生活習慣と脳トレ法
認知症は「治療が難しい」といわれることもありますが、実際には生活習慣を見直すことでリスクを下げることが可能です。特に、次の3つの習慣が脳の健康維持に有効とされています。
1. 身体を動かす習慣を持つ
ウォーキングやラジオ体操、簡単な筋トレなど、日常的な運動は脳の血流を促進し、認知機能の低下を防ぎます。国立長寿医療研究センターの調査では、週3回以上の運動をしている高齢者の方が認知症発症率が低いというデータもあります。
2. バランスの良い食事を心がける
地中海食や和食のように、魚・野菜・果物・オリーブオイルなどをバランスよく摂取することで、脳の炎症を抑え、神経細胞を保護すると言われています。特にDHAやビタミンB群は記憶力に関係するとされており、積極的に摂りたい栄養素です。
3. 脳を使う趣味・活動を続ける
囲碁・将棋・手芸・読書・日記・料理・音楽など、「考える」「手を動かす」趣味は、脳に刺激を与え、認知機能の維持に効果的です。最近では、「ピアノde脳活」や「そろばん脳トレ」など、シニア向けの活動も人気です。
不安を感じたときの相談先・次のステップ
認知症に対する不安を一人で抱え込む必要はありません。日本各地には、高齢者やその家族の相談に対応してくれる窓口が整備されています。
代表的な相談先
・地域包括支援センター(各市区町村):介護や健康、認知症に関する幅広い相談が可能
・かかりつけ医:日常の変化や症状について気軽に相談できる第一の窓口
・認知症疾患医療センター:より専門的な診断や対応が可能な医療機関
特に「最近ちょっと物忘れが増えたかも」と気になった段階で、まずは地域包括支援センターに電話をかけてみるだけでも大きな一歩です。
誰にでも起こりうる問題だからこそ、早めに情報を得て、安心して備えることが、健康的で前向きな老後につながります。
5.病院に行くべき?受診の目安と相談先の選び方
放っておいてはいけない症状とは
物忘れが気になるとはいえ、「病院に行くのは大げさかも」と感じてしまう方も少なくありません。ですが、次のような症状がある場合は、単なる老化ではなく、病気のサインである可能性があります。
受診を検討すべき主な兆候
・同じ話を1日に何度も繰り返す
・曜日や季節、時間の感覚がなくなる
・料理の手順や片づけができなくなってきた
・慣れた道でも迷ってしまう
・怒りっぽくなり、人との関わりを避けるようになる
これらの変化が「急に増えてきた」「以前とは違う」と感じたら、できるだけ早めに専門医に相談することが大切です。認知症ではなく、うつ病や他の疾患による可能性もありますが、どちらにせよ早期発見が回復・予防に役立ちます。
受診先は何科?地域の相談窓口も活用しよう
認知症の相談をする際は、最初に次のような窓口を利用するのがおすすめです。
● かかりつけ医(内科・家庭医)
まずは日常の変化を相談しやすいかかりつけ医に話してみましょう。必要に応じて、専門医や検査施設への紹介も行ってくれます。
● 認知症外来・もの忘れ外来
最近は、脳神経内科・精神科・老年科などで認知症専門の外来を設けている病院も増えています。「認知症外来」「もの忘れ外来」といった名称で予約を受け付けています。
● 地域包括支援センター
市区町村に設置されている高齢者向けの総合相談窓口です。「ちょっと気になる」という段階でも相談可能で、医療機関の紹介や介護サービスの案内もしてくれます。
ポイントは、「心配が小さいうちに相談しておくこと」。
早期であればあるほど、薬や生活改善で進行を遅らせることも可能です。勇気を出して一歩踏み出せば、不安はぐっと軽くなります。
6.まとめ|自己診断は第一歩。安心できる毎日のために
「最近ちょっと物忘れが増えてきたかも…」と感じたとき、その不安を放置するのではなく、自分で状態を確認することはとても大切な一歩です。
認知症自己診断テストは、そうした“気づき”を得るための手段として有効であり、変化に早く気づけば気づくほど、予防や対応の幅も広がります。
今回紹介したように、セルフチェックでは「自分の状態を数値化・見える化」でき、さらに生活習慣の見直しや医療機関の相談といった次のアクションにつなげることが可能です。
とくに70代以降は、体力や生活環境の変化に加えて、「社会とのつながり」や「役割を持ち続けること」が心の健康にも直結します。働くことや地域活動に関わることで、脳が刺激され、認知機能の維持にもつながるという研究報告もあります。
「自己診断テスト→生活改善→必要に応じて受診」というステップを踏むことで、将来への不安を軽減し、安心して暮らせる毎日を自分でつくっていくことができます。
どんな小さなサインでも、自分や家族のために「気づいて、動く」。それが、健康寿命をのばす第一歩です。
「健康のためにも、もう一度働いてみたい」そんな方は、シニア向け求人サイト【キャリア65】で自分に合った仕事を探してみませんか?