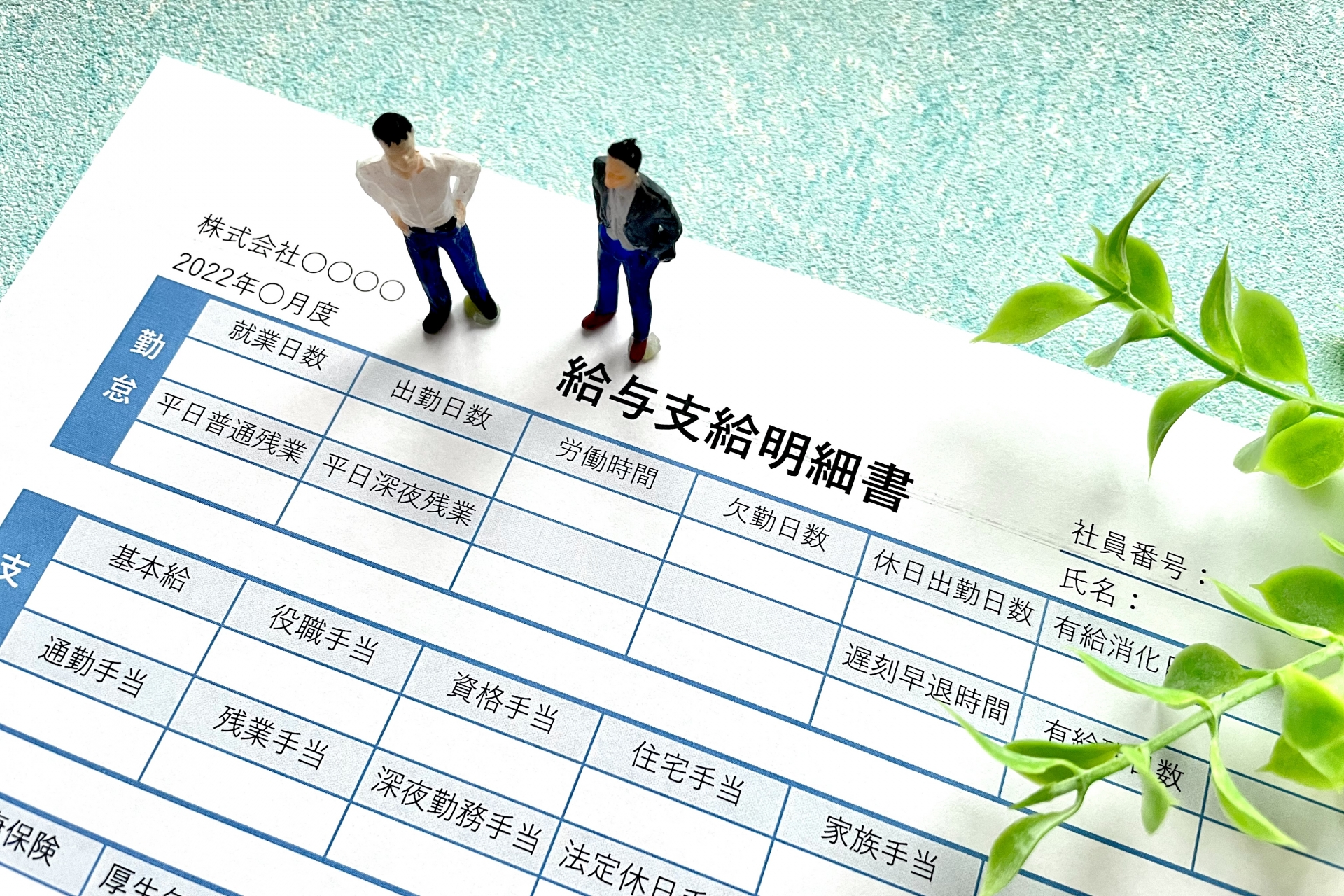1.はじめに|なぜ今「シニア従業員の給与減額廃止」が注目されているのか
近年、日本では少子高齢化が加速し、労働人口の減少が深刻な社会課題となっています。特に中小企業を中心に人手不足感は強く、経験豊富な人材をどのように確保・活用するかが経営上の大きなテーマです。そうした中で注目されているのが「シニア従業員の給与減額を廃止する動き」です。
従来は、定年後に再雇用される場合、給与が大幅に減額されるのが一般的でした。しかし、2021年の「高年齢者雇用安定法」改正により、70歳までの就業機会を確保する努力義務が企業に課せられたこともあり、企業の制度見直しが進んでいます。背景には、優秀な人材を引き留めるためには「公平な待遇」が不可欠だという認識の広がりがあります。
また、シニア人材は専門知識や技能だけでなく、若手社員の教育や現場マネジメントにも貢献できる貴重な存在です。その力を最大限に引き出すためにも、「年齢による一律の賃下げ」は見直されつつあるのです。
2.従来の再雇用制度と給与減額の課題点
日本の多くの企業では、定年を迎えた社員を「再雇用」という形で引き続き働ける制度を設けています。しかし、この仕組みには「給与減額」がセットになっているケースが少なくありません。具体的には、定年前の6割〜7割程度まで賃金が下がることが一般的で、厚生労働省の調査「雇用の構造に関する実態調査(高年齢者雇用実態調査)」でも、多くの再雇用者が「処遇に不満」を抱えていることが示されています。
このような給与減額は、企業側からすれば人件費を抑えながら雇用を継続できるというメリットがあります。しかし一方で、シニア従業員にとっては「同じ仕事をしているのに報酬が減る」という不公平感につながりやすく、モチベーション低下や早期離職を招く原因となっていました。
さらに、給与が下がることで生活設計に不安を感じるシニア層も多く、結果的に「働き続けたいのに働けない」「やむを得ず別の職場を探す」といった流れを生むこともあります。これは企業にとっても、せっかく育ててきた経験豊富な人材を失うことにつながり、損失は小さくありません。
つまり、従来型の再雇用制度は「人件費抑制」という短期的な利点はあるものの、長期的には組織力の低下や採用難の加速を招くリスクを抱えていたのです。
2.給与減額廃止の流れ|企業が導入を進める背景
ここ数年、シニア従業員に対する「給与減額」を廃止する企業が増えてきました。その背景にはいくつかの社会的・経済的な要因があります。
まず大きいのは 深刻な人手不足 です。帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2024年)」によれば、正社員が不足していると回答した企業は約50%に達しており、特に中小企業や建設・運輸・製造業で人材確保の課題が顕著です。この状況下では、シニア人材の活躍が企業の持続的な成長に欠かせないものとなっています。
次に、公平性への意識の高まり です。働き方改革や「同一労働同一賃金」の流れを受け、「年齢だけを理由に給与を減額するのは妥当なのか?」という疑問が社会全体で共有されるようになりました。特に優秀な人材ほど「給与に見合った評価」を重視する傾向が強く、賃金水準の維持が採用・定着の決め手となりつつあります。
さらに、法改正の影響 も見逃せません。2021年の高年齢者雇用安定法改正により、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務化されました。これにより、従来の「定年+給与大幅減額」という仕組みが時代に合わなくなり、制度を見直す企業が相次いでいます。
このように「人材確保」「公平性」「法制度」という3つの流れが重なったことで、給与減額を廃止する動きは単なる一部企業の試みではなく、今後のスタンダードになりつつあるのです。
3.メリット① 採用力の向上と人材確保につながる
シニア従業員の給与減額を廃止することは、採用市場において大きな競争力をもたらします。人手不足が深刻化する中で、求職者が企業を選ぶ際に「待遇の公平性」は重要な判断基準になります。
多くのシニア人材は「収入を補いたい」という経済的理由だけでなく、「自分の経験や能力を正当に評価されたい」という想いを持っています。そのため、給与が大幅に減額される再雇用制度を採用している企業よりも、正当な水準で給与を維持する企業を選びやすい傾向があります。
実際、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の「高年齢者の雇用に関する調査(2022年)」では、シニア層の約6割が「処遇の不満」が働き続ける上での障壁と回答しています。逆にいえば、給与水準を下げずに再雇用できる企業は、経験豊富な人材を呼び込みやすく、応募数の増加や定着率の向上が期待できるのです。
また、給与減額を廃止することは「企業ブランドの向上」にもつながります。公平な雇用慣行を打ち出すことで、社外からも「人を大切にする会社」という評価を得られ、若手人材や中途採用にも良い影響を与えます。結果的に、幅広い世代から選ばれる企業へと進化できるのです。
このように、給与減額廃止は単なるシニア人材への優遇策ではなく、採用力そのものを高める戦略的な施策 といえるでしょう。
4.メリット② 生産性・モチベーションの向上
給与減額の廃止は、シニア従業員の モチベーション維持 に直結します。長年培ってきたスキルや知識を正当に評価されることで、「まだ会社に必要とされている」という実感が生まれ、働く意欲が高まります。逆に、給与が大幅に減額されると「同じ仕事をしても報われない」という不満が募り、生産性の低下や早期離職につながりやすいのです。
実際、厚生労働省の「高年齢者雇用状況等報告(2023年)」によれば、シニア従業員が就業を継続する理由の上位には「生活の安定(約70%)」に加えて「働きがい・やりがい(約50%)」が挙げられています。収入面と心理面の両方を満たすことが、長期的な活躍につながるのです。
また、給与を維持することで 責任感や当事者意識 も高まり、単なる労働力としてではなく「組織を支える戦力」としての役割を果たすようになります。特に製造業やサービス業では、経験豊富なシニアが現場の安定化や若手育成に大きく寄与している事例が多く見られます。
さらに、給与減額廃止は 世代間の信頼関係 の強化にもつながります。若手社員にとって、シニアが正当に評価されている姿は「長く働ける職場」という安心感を与え、結果的に組織全体の定着率やエンゲージメント向上にも効果をもたらします。
つまり、給与減額廃止は「コスト増」ではなく、生産性とモチベーションを高める投資 と捉えるべき施策なのです。
5.法的なポイントと制度設計の注意点
シニア従業員の給与減額を廃止する際には、メリットが大きい一方で、法的な整合性や制度設計 に注意を払う必要があります。
1. 高年齢者雇用安定法との関係
2021年の改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となりました。この中で「再雇用制度」は重要な選択肢ですが、給与設計に関しては法律で一律の基準が設けられているわけではありません。そのため、各企業が自社の就業規則や労働契約の中で適切に定める必要があります。
2. 同一労働同一賃金の原則
2020年から段階的に施行された「同一労働同一賃金」のルールも無視できません。仕事内容や責任が同等であるにもかかわらず、年齢を理由に一方的に賃金を下げることは、不合理な待遇差と見なされる可能性があります。厚生労働省もガイドラインで「合理的な理由のない賃金差は違法」と明示しており、公平性の観点からも給与減額廃止は制度的に適合しやすいといえます。
3. 社内合意形成の必要性
制度変更を行う際には、従業員代表との労使協定や就業規則の改定が必要です。特に既存の再雇用者がいる場合は、待遇改善の経過措置や説明責任を果たすことがトラブル防止につながります。
4. 人件費シミュレーション
賃金水準を維持すると人件費が上がるため、短期的には負担増となる可能性があります。そこで重要なのが「人件費シミュレーション」と「生産性向上策の併用」です。シニアの経験を教育や品質管理に活かし、間接的にコスト削減や効率改善を図ることが求められます。
このように、給与減額廃止は「法的リスクの低減」と「組織力の向上」の両面を満たす施策ですが、制度設計には十分な準備と社内調整が不可欠です。
6.導入企業の事例から学ぶ成功のヒント
実際にシニア従業員の給与減額を廃止した企業の事例を見ると、その効果と工夫のポイントがよくわかります。
事例1:製造業A社
中堅の製造業A社では、熟練技能者の離職が相次ぎ、生産効率が低下していました。そこで再雇用時の給与減額を廃止し、業務内容に応じて従来と同等水準の給与を支給する制度に転換しました。結果として、シニア人材の離職率が大幅に下がり、若手への技能継承も進みました。特に品質管理の安定化によって、不良品率の低減など 数値での効果 が確認されています。
事例2:小売業B社
人手不足が深刻な小売業B社では、レジや接客業務を担うシニア従業員が重要な戦力でした。給与減額を廃止したところ、応募者数が従来比で1.5倍に増加。さらに、従業員満足度調査でも「会社に評価されていると感じる」との回答が増加し、職場の雰囲気が改善しました。
事例3:IT企業C社
専門性の高いエンジニアを抱えるIT企業C社は、技術の継承と人材不足解消のため、シニア層の給与を維持する制度を導入しました。その結果、若手社員との共同プロジェクトで成果が向上し、シニアがメンター役として機能。若手定着率の向上にも寄与しました。
これらの事例に共通するのは、給与を維持するだけでなく、役割設計やキャリアパスを明確化 している点です。単に「給与を減らさない」だけではコスト負担で終わってしまう可能性がありますが、シニアの強みを最大限に活かす仕組みを併用することで、組織全体のパフォーマンスが高まります。
つまり、給与減額廃止の成功のカギは「処遇改善+役割設計」のセット導入にあるのです。
7.まとめ|人手不足時代に選ばれる企業になるために
シニア従業員の給与減額を廃止する動きは、単なる福利厚生の改善ではなく、人手不足時代を勝ち抜くための戦略 として注目されています。
従来の再雇用制度では、給与減額がシニア従業員の不満や離職を招き、結果として企業の人材流出や生産性低下を引き起こすことも少なくありませんでした。しかし、近年の流れとして「同一労働同一賃金」「高年齢者雇用安定法の改正」などを背景に、公平で納得感のある制度設計が求められています。
給与減額廃止によって得られるメリットは大きく、
・採用力の向上(応募者数の増加、企業ブランドの強化)
・モチベーション維持による生産性向上(離職防止、現場の安定化)
・若手育成への貢献(技能継承やメンター役としての活躍)
といった形で組織全体に波及します。
もちろん、人件費増という課題もありますが、シニア人材を戦力として活かすことで十分に回収可能です。むしろ「人を大切にする企業」としての評価が高まることで、長期的には採用・定着の両面で大きなリターンを得ることができます。
人手不足が続くこれからの時代、企業が選ばれる条件は「年齢に関係なく正当に評価される環境」を整えられるかどうかにかかっています。給与減額廃止は、その第一歩となる取り組みなのです。
経験を活かせるシニア向け求人が多数!今すぐ「キャリア65」で新しい働き方を見つけてみませんか?